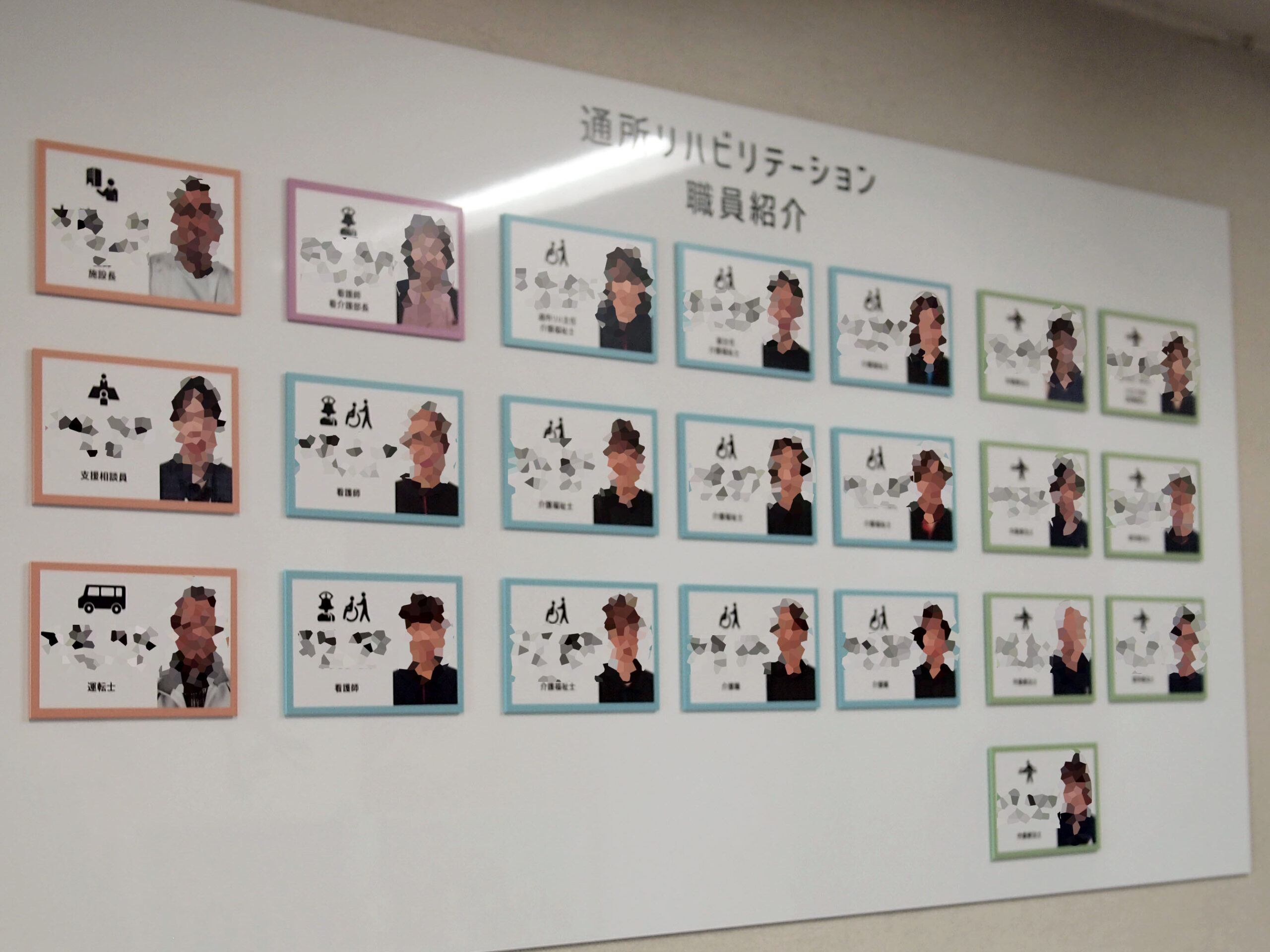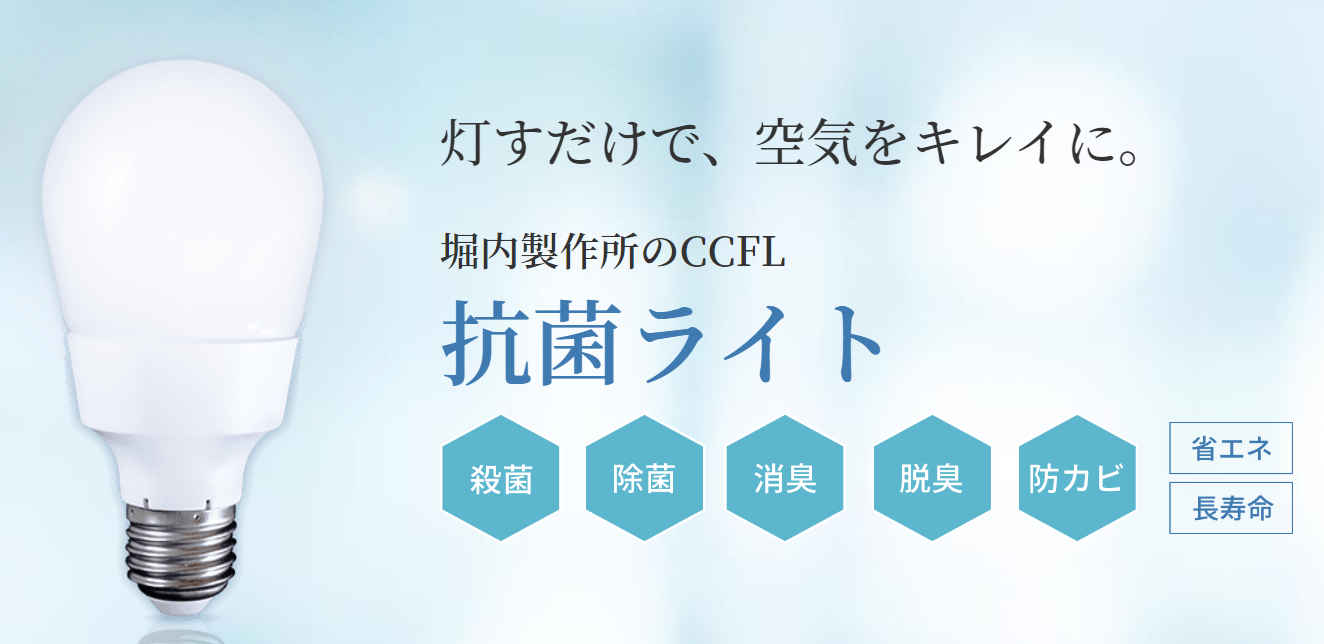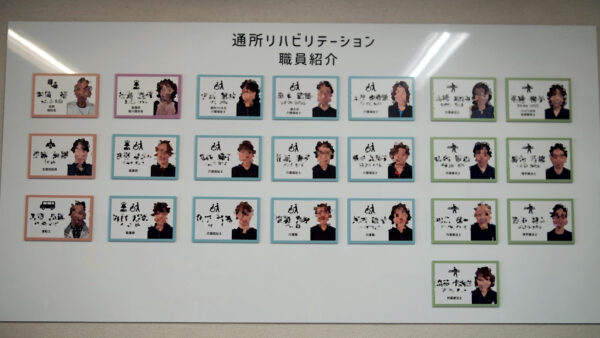私たちの身の回りは、さまざまな色に囲まれています。色には情報をキャッチして識別する機能的な役割のほかに、人の感情や情緒などの心理に働きかける効果もあるといわれています。
認知症の方が過ごす医療・介護施設においても、空間認知を助けたり、精神を安定させて穏やかに過ごしたりできる環境をつくるために、色彩の効果を活用することが重要です。
医療・介護施設の管理者のなかには「色が認知症の方の行動や感情にどのような影響を与えるのか知りたい」「色の効果を活用して安心して過ごせる環境を整えたい」などとお考えの方もいるのではないでしょうか。
この記事では、認知症と色との関係性を踏まえつつ、安全で居心地のよい施設環境をつくるための色彩活用のポイントを解説します。
認知症と色の関係性
視覚から得られる情報は、人の五感による知覚の約8割を占めているといわれています。視覚情報の一種に含まれる“色”には、大きく2つの働きがあります。
▼色の働きと役割
| 働き | 役割 |
| 機能的効果 | 文字や形を見やすくして視認性を高める文字や形を目立ちやすく強調して、注目・注意を引く文字や形の内容を理解しやすくする(明視性・可読性を高める) |
| 心理的効果 | 色が持つイメージ・雰囲気から感情を喚起させる色から連想させるイメージを活用して情報を伝える |
認知症になると、加齢による色覚の変化のほか、視力・周辺視野・視覚情報の処理能力などが低下している場合があり、モノや空間を認識するのが難しくなることがあります。
認知症の方の自立した行動を支援しつつ、過ごしやすい施設環境をつくるには、機能的効果と心理的効果の2つの要素を考慮して、壁や設備などの配色を工夫することが重要です。
安全で居心地のよい施設環境をつくる色彩活用のポイント
色の機能的効果は、認知症の方の空間認識を助けるために活用できます。記憶に頼らずに環境のなかで状況を理解しやすくすることで、自立した行動を促せるようになります。
また、色の心理的効果については、不安や混乱、孤独感などを和らげて、居心地よく安心感のある空間をつくるために活用することが可能です。
ここからは色が持つ機能的効果・心理的効果を取り入れた、施設環境づくりにおける色彩活用のポイントを解説します。
01 サインの地色と図色にコントラストをつける
施設内に設置するサインには、認知症の方が記憶に頼らずにその場にある情報で行動しやすいように誘導する役割があります。
扉や通路に文字またはピクトグラムを用いたサインを設置する際は、背景となる地色と図色にコントラストをつけることによって視認性を高められます。色の明るさ・暗さを示す明度に対比をつけることがポイントです。
また、サインの地色と図色は、識別しやすい色の組み合わせを選ぶことが重要です。以下のような色の組み合わせは、識別しにくい可能性があるため避けるほうがよいといえます。
▼識別しにくいサインの地色・図色の組み合わせ例
画像引用元:国土交通省『4.色覚障害者に配慮した設備整備のあり方の提案』
02 扉や手すり、家具の色が同化しないようにする
医療・介護施設において、認識してほしい場所の注意を引くために、色をつけて同化しないようにすることもポイントの一つです。
扉や手すり、家具などが周辺の壁・床と同化しないように色をつけることで、境目を判別しやすくなります。これにより、目的の場所を認識して行動しやすくなるほか、色の区別がつきにくいことによる転倒やつまずきなどの事故を防げます。
▼色の区別をつける例
- 自室やトイレの扉と壁の色にコントラストをつける
- 壁と手すり・扉と取っ手の色にコントラストをつける
- 床の色と同化しにくい椅子・テーブルの色を選ぶ
03 段差の有無に合わせて床の色を工夫する
施設内の廊下や部屋との境目などの段差のない床部分については、色を統一することが重要です。床の色にコントラストがある場合、段差があるように見えてしまい、立ち止まったり、バランスを崩して転倒したりする可能性があります。
トイレと廊下、部屋と廊下などのつながりを認識しやすいように、コントラストをなくして明度を統一することがポイントです。
反対に、階段の踏み板や浴室の浴槽・洗い場などの段差のある場所については、色のコントラストをつけて高低差を認識しやすくすることも重要です。
なお、認知症の人は、大きな模様や強い色に対して不安を覚える人もいるため、床の模様は落ち着いたものを選ぶ必要があります。
04 用途に合わせた色を取り入れる
医療・介護施設の内装には、用途に合わせた色を取り入れることがポイントです。
色によって人に与える印象が変わり、そこから生まれる感情にも影響します。色が持つイメージと心理的効果を知り、医療・介護施設の各スペースの用途に合った配色を取り入れることが有効です。
▼医療・介護施設で取り入れるとよい色と心理効果
| 色 | 色が持つ印象 | 心理効果 |
| 黄 | 元気・希望・愉快・活発 | 明るく活発な気持ちにさせる胃腸の働きを活発にさせる |
| 橙 | 陽気・暖かい・楽しい | 安心感や暖かさを思わせる楽しく朗らかな気持ちにさせる |
| 緑 | 安らぎ・若々しい・癒し・優しい・調和 | 穏やかでリラックスした気持ちにさせる身体の疲労を癒す |
| 青 | 信頼・爽やか・誠実・知的・落ち着き | 緊張や不安を和らげる爽やかな気持ちにさせる集中力を促進させる |
| 茶 | ぬくもり・落ち着き・信頼 | 温かみやぬくもりを感じさせる気持ちを落ち着かせる |
| ベージュ | ナチュラル・優しい・家庭的 | 緊張を緩める安心や優しさを感じさせる |
ただし、鮮やすぎる色は印象がきつくなり、見る人に圧迫感や疲労を感じさせる可能性があります。認識しやすい明度を確保しつつも、親しみやすく疲れにくい柔らかい色味を選ぶことがポイントです。
▼色の心理効果を利用した施設づくりの例
- レクリエーション部屋には、活動的で陽気なイメージのある橙や黄の色を小物・絵などで取り入れる
- 利用者の自室には、心を落ち着かせてリラックスできるようにベージュのカーテンや緑の観葉植物を取り入れる
色彩による工夫に加えて、施設の雰囲気を決めるのは「人の安心感」です。
初めて訪れたご家族や利用者にとって、顔が見える環境は大きな安心材料になります。
▶ 『スタッフ紹介パネル』は、スタッフ一人ひとりの顔と名前を掲示することで、
・利用者にとって「親しみやすい存在」に
・ご家族にとって「信頼感が高まる環境」に
つながります。
空間の安心感は色だけでなく、人のつながりからも生まれます。
安全で居心地のよい医療・介護施設をつくる色彩活用のポイント
この記事では、医療・介護施設における色彩活用の基本についてご紹介しました。
色には、空間認識を助けたり注意を引いたりする機能的な役割のほか、感情を喚起する心理的効果があります。
認知症の方には、サイン表示や床・壁・扉のコントラスト、落ち着きを与える配色などが特に重要です。
『ケアツール Iggy』では、こうした環境づくりを支える製品を多数ご用意しています。
衛生面の強化や利用者の安心感アップにつながるツールで、施設運営をサポートします。
認知症ケアの空間づくりでは、色彩だけでなく「人の存在を感じられる工夫」が重要です。
『スタッフ紹介パネル』は、施設に訪れる方が最初に目にする場所で安心感を生み、
利用者とスタッフの距離をぐっと縮めます。
また、目に見えない清潔感を支える『抗菌消臭ライト』も、快適な空間づくりに役立ちます。